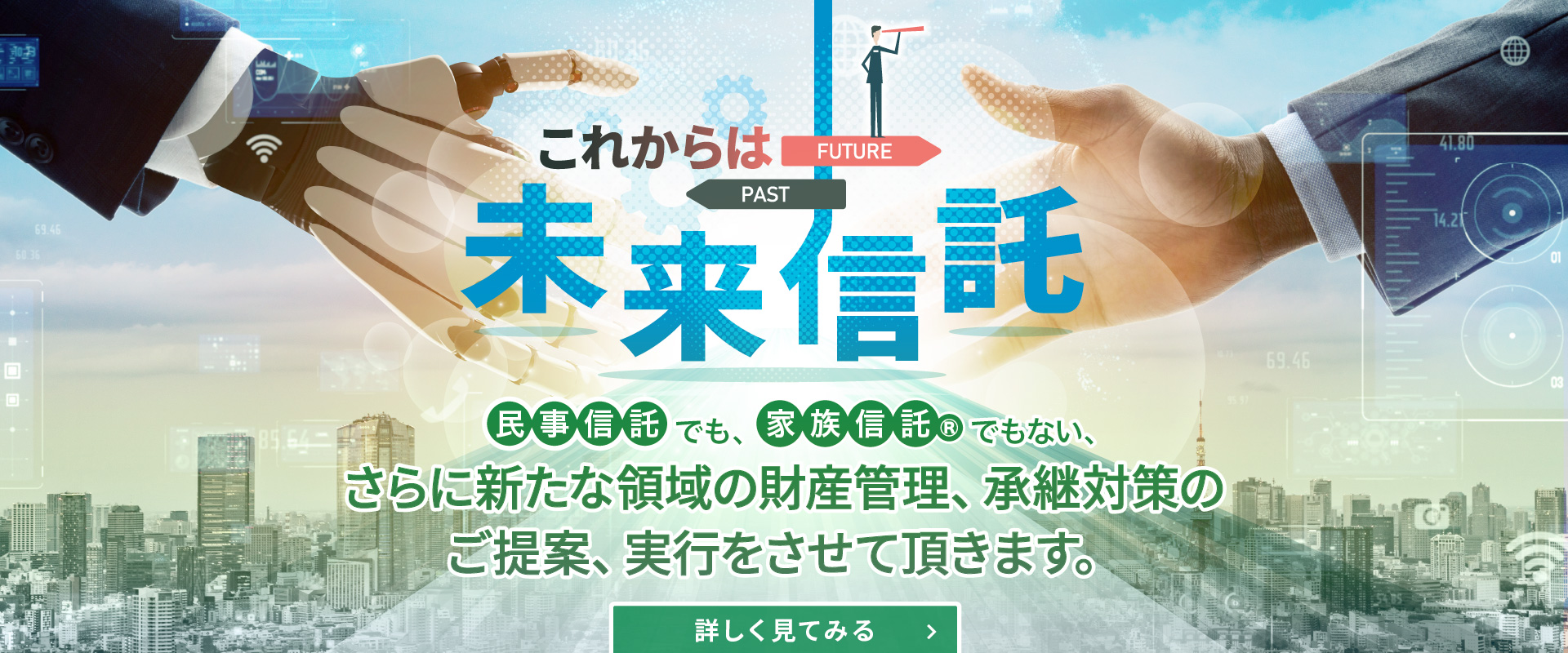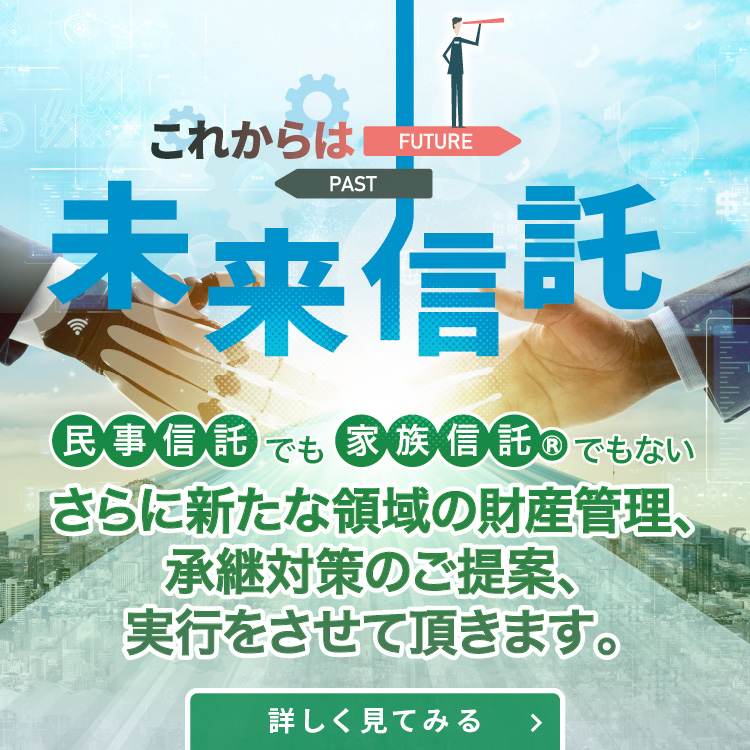ブログ
2021.09.07
逆ピラミッド型の人口構造
日本も「少子高齢化社会」と言われて、社会問題化されていますが、
妊婦さんも新型コロナの感染予防対策を見ると、本当に政府は力を入れているのかと、
疑問に思います。
中国も、かつての「一人っ子政策」で、少子高齢化社会を迎えております。
しかし、地球規模では、人口増加が問題となっているという、国によっては政策を
変えないといけません。
『逆ピラミッド構造の人口』
これを最近、セミナーでお話するのですが、
どの国の政策においても、人口構造は「ピラミッド型」でしか、対策を講じたことが
ありません。
経済成長、発展、社会保障制度等々、若い世代が多くて、高齢世代になるにつれて
少なくなる。
この人口構造でしか、政策を考えたことはないでしょう。
『逆ピラミッド構造』に人口がなると、今までの経験、通念、方式が通用しなくなります。
誰も経験したことのない社会構造ですから、今まで必要な事が不要になったり、
不要な事が必要になったり、ここでも逆転が生じるでしょう。
なので、中国は『宇宙』に目を向けて政策をしているのかもしれません。
月に基地を建設する計画があるようですから。
それほど、大胆な方向転換を日本も早めにしないと、いけないのかもしれません。
現状の社会制度や法律も勿論です。
千年以上続いた、日本が世界に誇る『古都・京都市』も財政がピンチです。
これも、『ピラミッド型』の政策を続けた仇が出た結果かもしれません。
2021.09.06
東京パラリンピック閉会そして…
昨日、東京パラリンピックの閉会式がありました。
あの舞台に立つまでに、想像を越える壁を乗り越えて活躍された選手の皆さま、
本当にお疲れ様でした。
前向きに生きる事の大切さを、教えて頂きました。
コロナ感染禍の中、一大イベントが終わりましたが、
次は、日本にリーダーになる方に注目が集まりますね。
総理大臣の伝家の宝刀である、解散権を行使せず、というより
現状では、行使できない状況でしょうか、菅総理は次の自民党の総裁選には
出馬されず、衆議院議員も任期満了で、選挙という流れになりました。
このパンデミックの中、新たな希望、道を示してくれるリーダーになる方は
いらっしゃるのでしょうか。
日本の岐路になるであろう、選挙になりそうですね。
できれば、強い野党の存在があれば、選択肢は増えるのですが。
2021.09.02
デジタル庁発足も・・・
9月1日に、菅総理の肝いり政策のデジタル庁が発足しました。
しかし、衆議院議員の選挙で、菅総理も内心、それどころじゃない、って言うのが
本音でしょうか?
しかし、日本は他の国から見てもデジタル途上国です。
まだFAX、紙ベースの資料ですし、行政の申請も紙が、他のどの国よりも
使っております。
先ずは、国会からデジタル化をして、お手本を見せて欲しいと思います。
この気候変動も、森林の伐採から始まり、現在の災害に繋がっていると
考えられます。