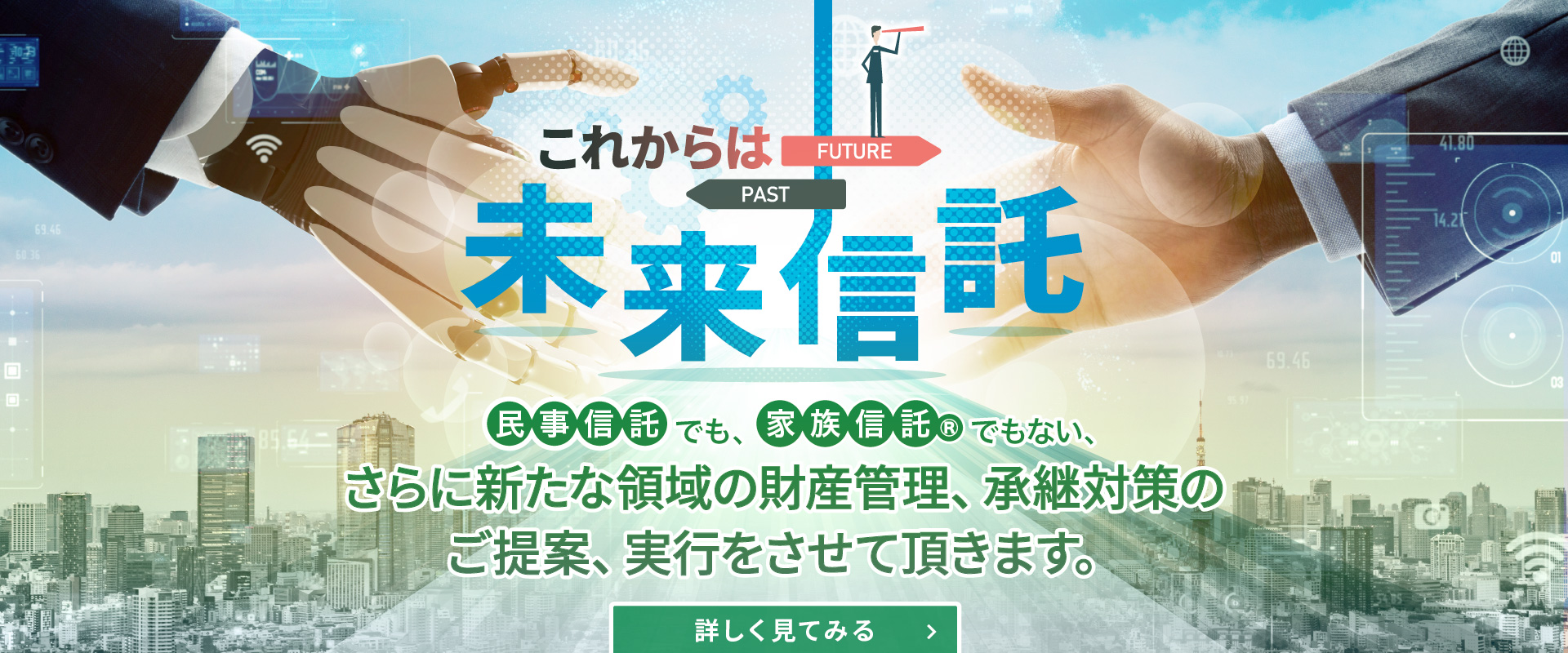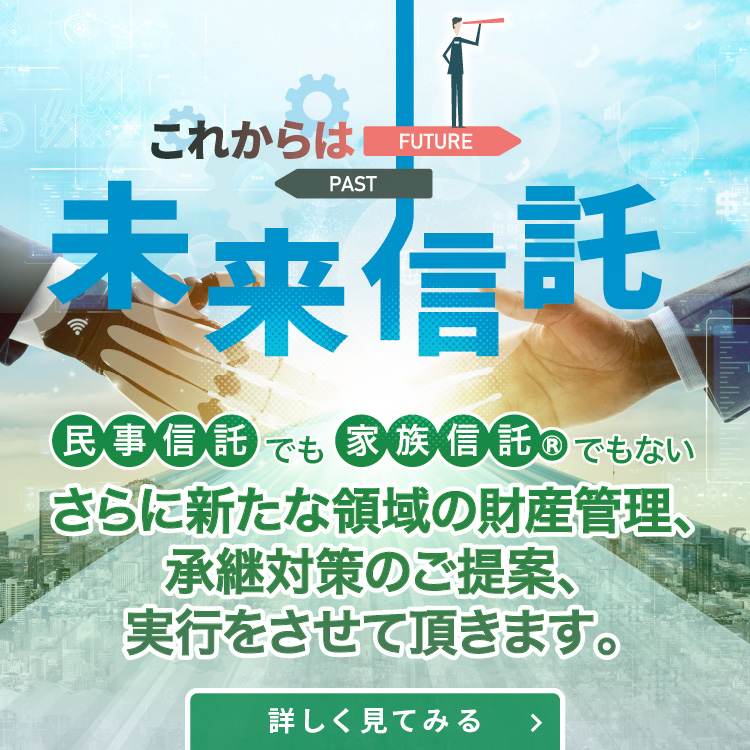ブログ
2022.05.12
歴史は繰り返す⁉
お隣の韓国の大統領が交代しました。
今度の方は、大統領府から出て、国民に近い存在になりたいとのことで、
都心部に大統領の執務室を移転されたようです。
親日派とも言われている様です。
また、あまり報道されていないですが、フィリピンの大統領も交代したようです。
マルコス大統領。
そう、80年代、独裁政治と、国家予算を横領して国外追放された当時のマルコス大統領の
息子さんです。
80年代、当時のマルコス政権は、経済発展を遂げた裏で、
国家予算を夫人のイメルダ夫人が贅の尽くす限りの生活に費やし、
国民を苦しめたという、当時の報道が私の幼い頃の記憶にございます。
現大統領のマルコス大統領の支持層は、若い方が多く、かつての80年代のマルコス政権時代を
勉強していない世代のようです。
ちなみに、今回のフィリピンの大統領選挙には、伝説のボクサー、パッキャオ氏も立候補されていたようです。
「歴史は、繰り返す」と、言われますが、そうならない様に祈るのみです。
2022.05.06
ビジネスで大切な事は、初心さ(うぶ)を持ち続ける事
ジャニーズ事務所から「なにわ男子」が「うぶLOVE」というデビュー曲でデビューしました。
アイドルの話をするわけではないのですが、ふと思い出した言葉とリンクしました。
「ビジネスで大切なこと、いや、物事に取り組む姿勢として
『初心(うぶ)さを忘れない、持ち続ける人』が成功、達成する。」
これは、大学を卒業して、入社した呉服店の社長から頂いた言葉です。
20代前半の私にはあまり、いや、意味が良く判らなかったのですが、
40歳を越えた今、当時、社長が伝えたかった本心が自分なりに理解出来るように、
なりました。
人生、経験は重要です。
しかし、その経験が時として、挑戦することを妨げることになります。
「これでは、以前、失敗したから、この事は止めておこう」
「もう、歳だから、止めておこう」…
そうです、ある意味、経験は失敗を回避する選択肢を与えてくれます。
しかし、それ以上の事をしようとすると、「失敗したから」という経験の結論で
先に進む道を自分で閉ざしてしまう事になります。
アメリカのGAFAといわれる巨大組織は、20年前には、存在しませんでした。
おそらく、これほど巨大な組織を作れる発想は、常識のある人には「不可能」と判断するのだと
思います。
しかし、この巨大組織を作った経営者は、何百という挫折を経験しながらも、
「初心さ」を忘れずに、いや、持ち続けたから成功したのだと思います。
幼少時期も子どもは、好奇心旺盛です。
なぜなら、「初心」だからです。
勿論、経験をして、学習することもあります。
しかし、何かをしないとアクションをしないと、リアクションもわかりません。
「初心忘るべからず」と、言われるのも、この語源かもしれません。
何かにつまずいた時、壁にぶつかった時、悩んだ時、
「そのことをはじめた『初心』」を、もう一度、思い出してみると、
何かのヒントが見つかるかもしれません。
そんな時は、「決心した場所に行く」や「その当時の友人に会う」、「後押ししてくれた音楽を聴く」
と、不思議と『初心な自分』に出会えるかもしれません。
2022.05.02
相続税対象ではない不動産オーナーにも切実な問題
「相続税の節税のために収益マンションを沢山、購入しているんです」
と言う、俗に言う「タワマン節税」が、先日、最高裁で否決(認めない)という判断が下された。
(※詳しくは、またお知らせで挙げます)
「相続税がかからなくて、ホッとした」
という、不動産オーナーさんは、多いです。
果たして、相続税だけを気にされるのは、注意が必要です。
多くの不動産オーナーの方は、不動産管理会社を設立されて、運営されておられます。
実は、その不動産管理会社(株式会社、有限会社)の、株主という地位も相続の対象となります。
また、会社の株価と資本金に繋がりはありません。
会社の株価は、会社保有の資産によって算定されます。
また、収益マンションは、「借り手」が居て成り立つビジネスです。
しかし、少子高齢化、核家族化、高齢者世帯の増加で、「借り手」が見つかりにくい時代です。
「心理的瑕疵」、俗に言う、事故物件となると、市場価格から3割から5割減の家賃又は「借り手」が居なくなり、
収益どころか、赤字しかならないマンションが多くなるでしょう。
Youtubeでは、Googleマップのストリートビューを使用した「事故物件の紹介サイト」や
有名な「大島てる」のサイトには、詳しく紹介されています。
また、大修繕には、これからの円安傾向で資材の高騰によって、修繕費がかかる事は容易に想定できますし、
また、解体費用も建設費用並みに係ることがございます。
「収益マンションで相続税節税」は、二重いや、それ以上のリスクが伴います。
是非とも、早めの対策をお勧め致します。