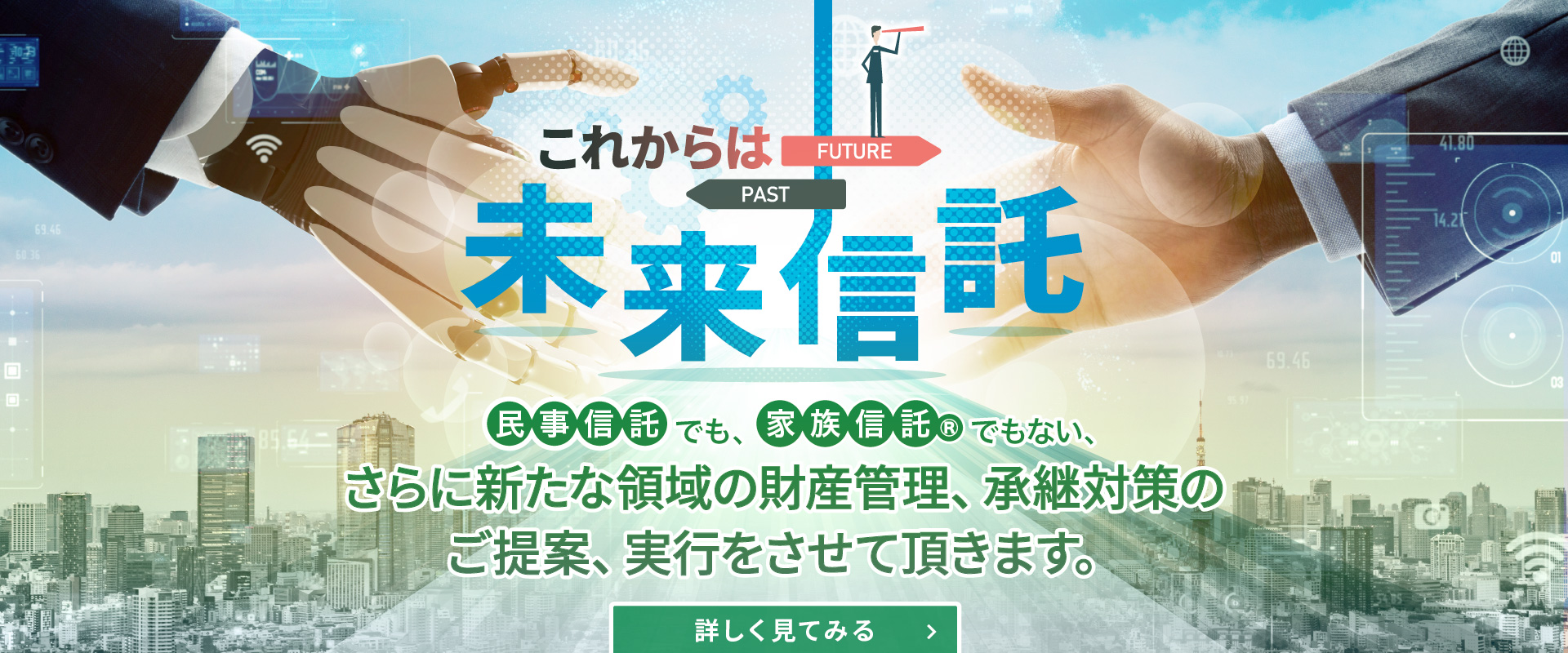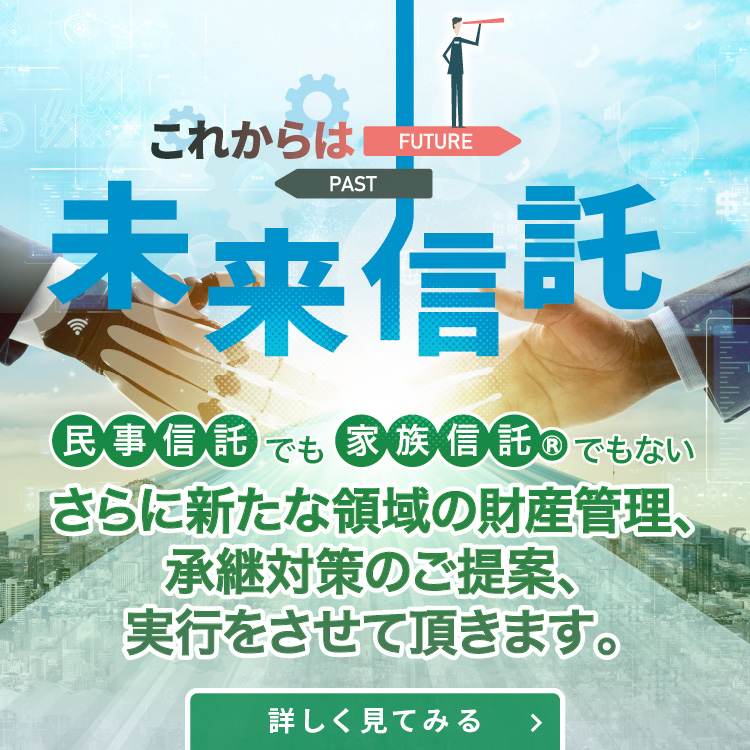ブログ
2022.05.18
戸籍法改正案「キラキラネーム」は、どこまで許容?
かつて自分の子どもの出生届で「悪魔」という名前をつけて役所に提出したところ、
役所が受理しなかった時間がございました。
親となる方の道徳観や倫理観が、その時代から色々と議論される様になりました。
その数年後、子どもに俗に言う「キラキラネーム」をつける親が急増した時代がございました。
「海(まりん)」...
現在、戸籍にはフリガナがなく、どのようにお読みする名前がわからない場合もございます。
そこで、戸籍に氏名にフリガナをふるとうい改正があるようです。
法律実務をしていると、大変助かります。
また、この「当て字」や「キラキラネーム」を、法律でどこまで許容するのか、
法制審議会で議論されているようです。
かつては、親が名前を託して「こんな子になって欲しい」や「画数で名前を決める」など、
親としての「願い」があったようです。
今でもあると、思いますが、行き過ぎた「キラキラネーム」は、幼少期はいいかもしれませんが、
社会人になって、その子がどう思うか、も考えてあげるべきではないかと思います。
「名は体を表す」とあるように、子どもの将来の幸せにために「名前」を命名して欲しいと
願います。
2022.05.16
【注目!】最高裁が「過度な相続節税に対してNO」という判断を下した!
これからの「相続税節税対策」は、より慎重さを要します。
私は、一貫して、「空地に賃貸物件を金融機関から融資して、建設して相続税を節税する」という
スキームを、お勧めしませんでした。どちらかというと、反対の立場でした。
(そもそも、その相続税を融資(負債)で減らしても、返済は残るし、賃貸物件の稼働率についても疑問が
ございました)
これから、経済誌などで暦年贈与の廃止と伴にトピックとなると思います。
資産承継・事業承継対策を生業としていると、税法の基礎的な知識は必要です。
詳細は税理士さんにお願いしますが、税法も言わずもがな法律です。
日本国憲法を学んだ時に、「租税法定主義」「公平性・平等性」「二重課税の禁止」が
税法の基礎としてございます。
脱線しますが、憲法は国、国家権力を縛る法律です。
王政の恣意的な政治から、自分たちの事は自分たちで決めるという「民主主義」への
意向により、資本主義国家が成立しました。
憲法の原理原則から言えば、「刑法」「税法」は、違法になります。
しかし、それでは、国家統制が取れないため、国民が原理原則の例外策をきちんと「法律」として
決めて、運用するようになりました。
話を戻しますが、今回の最高裁の判決は、実務界に大きな影響を与えると思います。
安易に負債額を増やして、相続税の負担を逃れて、負債で購入した不動産を売却すれば、
相続税の節税いや、相続税が0円になると、税理士が税務署に申告して、国税はそれを
認めない、では、最高裁で判断を仰ごうとしたものです。
国税通達で、このような相続税の価格算定を認めているものが、あったようですが、
最高裁は、やはり、「客観性」での判断を重視したようです。
法律家の視点からすると、予算等に関わる事に関しては、憲法、判例から推測すると、
行政(国税等)に、余程の瑕疵や公序良俗に反しない限り、行政側を支持する判例が多いです。
「法律」的な判断を下すのは、大きな最高裁の役割ですが、税という国家予算に関わることに
関しては、より慎重な判断を今までもして来た様に思います。
今回の最高裁の判断は、私、一人の法律家として「もっともだ」と、支持します。
詳しくは、本判決を含め、近時の民事信託に関する裁判例に関して解説、これから実務家として
あるべき事をセミナーで、お話したいと思います。
興味のある方は、受講の程、よろしくお願い致します。
2022.05.13
『壁』をどう乗り越えるか!
この季節になると、未だに思い出します。
司法書士試験の出願期間の丁度、中日だと思います。
当時は、全国47都道府県で受験できていましたが、確か数年前から各法務局(面接試験)の
開催する場所でないと、首都圏、関西圏は除いて受験地が制限されたようですね。
おそらく、受験者数の減少から、コストがかけられなくなっているからだと思います。
先日、「初心さは大切だと」お伝えしました。
私は、ベテラン受験生と呼ばれるカテゴリーで合格しました。
当時は、一緒に勉強していた方々が先に合格されて、焦りもあり、精神的にもきつかったです。
しかし、今、思うと、その受験生時代に勉強したことが、今の実務やセミナーで講師させて頂くときに
物凄く、役立っています。
「これだけで、合格」「短期合格本」とか、たくさん書店にありますが、
「本試験合格」という目的で、〇×で覚えて、本試験に合格しても、
合格後、大変苦労すると思います。
現在、多くの法律の改正、実務での変更、IT化など、〇×では、処理できない問題ばかりです。
登記実務も数年後、大きく変更されると私は予測しております。
でも、「司法書士」という職種は、存在し続けると思います。
登記は、従たる業務になるとは思いますが。
どの士業、職種も大きな分岐点にあります。
今まで、当たり前の職業が存在しなくなる恐れもあります。
なので、「壁」を目の当たりにしても、「壁」の、その先を見通して下さい。
大きな「俯瞰」した視野で、考えると、ほぼ、その本試験という壁は、大した事ないと思います。
でも、よくわかります。
「壁」を目の当たりした不安な気持ちを。
もうひとつは、本試験に受験できるという事、環境、周りの方々に感謝してみて下さい。
私も、合格した年の本試験前日は、近くの「神社」に「感謝の気持ち」をお伝えしました。
家族にも「今まで、勉強させてくれて、ありがとう」と、伝えました。
そこには、「壁」に対する不安は、ありませんでした。
何故、「感謝」するかと言うと、当たり前に「受験」しているようですが、
色々な事情で受験できなくなった方、受験を諦めた方も多く存在します。
世界の現況を見ても「当たり前」の事など、何一つ存在しないのだと。
明石家さんまさんが「生きているだけで丸儲け」と、よくおっしゃいますが、
その通りだと思います。
「感謝」の気持ちさえ忘れなかったら、大丈夫。