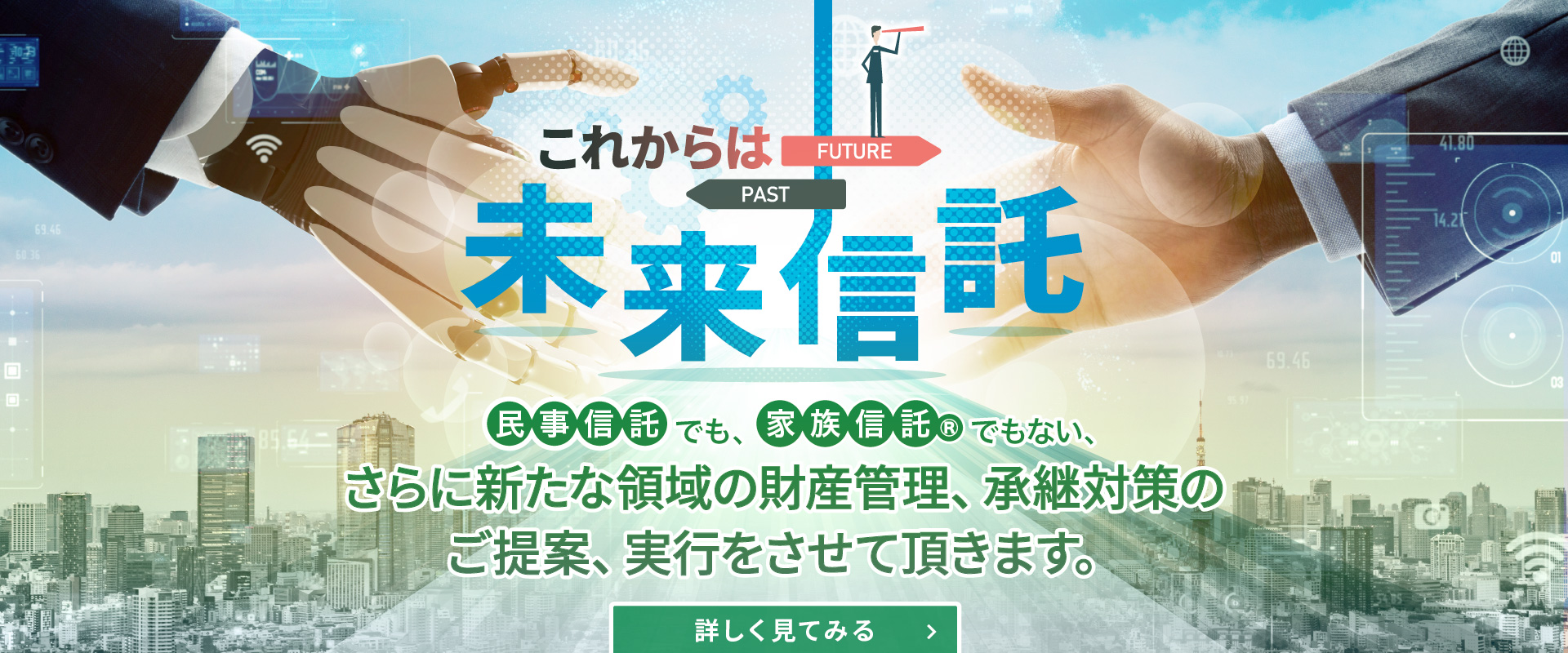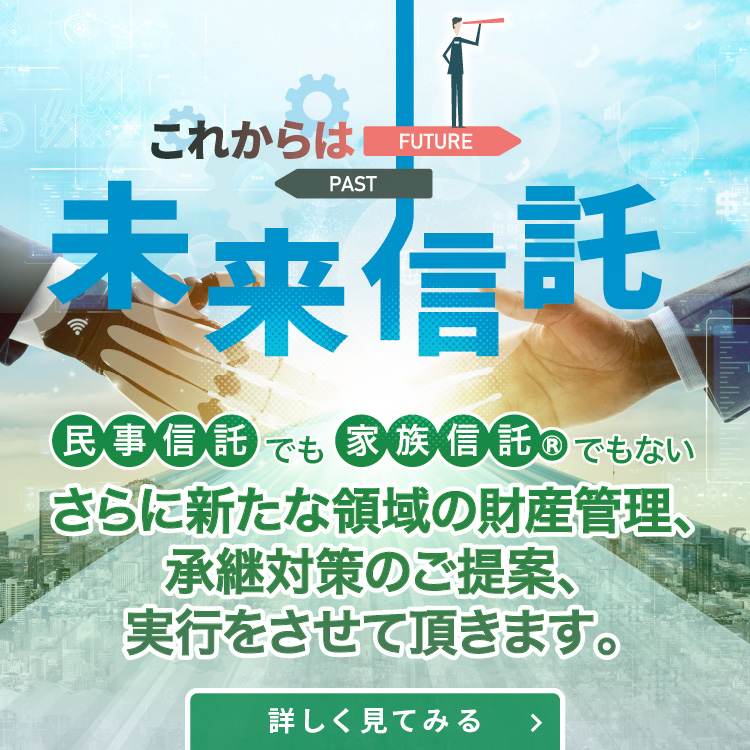ブログ
2021.08.03
これからは「乗せる」仕事の時代⁉
興味深い話をYouTubeで聴いたので、ご参考までにと思いまして。
東京の司法書士法人アコードの近藤司法書士がYouTubeしていらっしゃって
拝見するのですが、私が7年前に事務所の開業にあたって、大学生の時に所属していた
ゼミの先生がアドバイス下さったことと、共通する内容で、「なるほど」と、
改めて納得したので、投稿します。
近藤司法書士は、YouTubeで福岡のコンサルの方に「仕事は大きく3種類に分けられる」と
お聴きになったそうです。それは...
①「抜く」仕事
②「張る」仕事
③「乗せる」仕事
①は、日本の従来の職業形態で、酒屋の卸業や物販の小売業、又は我々士業の従来業務
すなわち、価値の提供は誰がしても変わらない、価格競争になりやすい、150円のお茶を
買う際に、コンビニでもスーパーでも自動販売機でも代わる仕事です。
司法書士で言うなら、「登記業務」といったメイン業務、税理士で言うと「記帳代行、申告業務」
行政書士なら「許認可業務」。どの同士業がしても基本、結果が同じでないといけない業務です。
(そうしないと、登記も許認可業務も通りませんから)
この業務を生業に出来たのは、社会が成長期であったからだと思います。
②は、不動産業者や株の投資家が、安く対象を買い、高く他に売って利益を得る仕事です。
株式投資はすでにAIが行っているケースも多くなり、不動産に関しても何かプラスアルファが
必要なお仕事だと思います。
③は、これからも生き残れる仕事です。
その人にしか出来ない価値を提供する、提案型のお仕事です。
これは、かつての国家資格の業種でしたが、既にDX(デジタルトランスフォーメーション)
AI(人工知能)、ディープラーニングによって、ビックデータがあれば、AIが答えを最適なものを
出してくれる世界になりましたので、国家資格は残念ながら、これには、もう該当しないと思います。
しかし、国家資格のメイン業務が減少しても、そこに附随する業務がメインになれば、
十分に生き残れると私は思っております。
ここで7年前、開業するにあたり、私の恩師がはなむけの言葉として下さった言葉を
思い出しました。
『これからは、司法書士の日下君ではなく、日下君が司法書士をしているから、相談してみよう
と、思ってくれるファンを誠実にたくさん増やしていって下さいね。初めは大変だと思うけど、
出来るはずだよ』と、おっしゃって頂きました。
今も、それを実践し続けているので、困難な事や壁も多いですが、『なりたい姿』があるので、
お蔭さまで、仕事をさせて頂いております。
私にしか出来ない、仕事、ご提案、「何かあると、ふと頭をよぎる存在」になれるように
改めて頑張って行こうと思います。
岡山も新型コロナ感染拡大で、明日から飲食店では時短要請が始まります。
まさか、ZOOM等を通して会議をする事は、遠い将来の事と思っておりましたが、
実際、今、活用していますよね。
「こうしたら儲かる」「こうしたら成功する」「こうしたら合格する」といった
「出来る本」が、巷にありますが、それらは通用しなくなる時代だと思います。
個人的感想を言うと、それをして成功したり、儲かったりするのは、「たまたま」という
運のしろものだと私は思っております。
自分で決めた「WAY」を、歩んでいきたいと思います。
2021.08.02
『日常生活の引力』が成長、変化を妨げる⁉
最近、お仕事を一緒にしている方と話していて、大いに気付く事がありました。
『日常生活という引力が強いと、新しい事の手を出しにくくなりますよね。
今のままで、いいか、と思うと何もしなくなりますよね。』
う~ん、なるほど。
お判り頂けますか。
人間、経験した事については当然のように、恐怖もなく手を出せる事が
多いですが、未知の経験は想定が付かないので、恐怖と危険を恐れて、
手を出さなくなる。
別に新たな未知の分野の手を出さなくても、現状の仕事でご飯が食べれるから、
今のままで、いいや。
って、感じる事です。
そうですよね、生活できていれば、未知の新たな分野への挑戦をしなくても
いいですよね。
しかし、今している仕事や業務で10年先、いや次の「パリ五輪」のときに
生活できているでしょうか?
『♪今以上を欲しがるくせに、変わらない愛を求め歌う♪』
ミスチルの『くるみ』という曲の歌詞です。
真にこのことでしょう。
今以上が欲しいけど、変わらないでもして欲しい。
これは矛盾することです。
なぜなら、今以上になるには変化を許容しないといけません。
でも、変わらないでいて欲しいのなら、『今以上』を求めることは、
無理です。
年齢を重ねるごとに、時代の変化に疎くなるというか、
もしかしたら、受け入れたくないという気持ちが強くなるのかも
しれません。
そうすると、年齢を重ねても好奇心の強い人しか、
この変化、成長をすることが難しくなるのかもしれません。
私は、今でも好奇心が強い方ですので、
新しい事に興味が湧き、知りたくなる。
これは、欠点のように思えてきましたが、最近になって長所かな
と思うようになりました。
司法書士試験の時も「受験では、これだけの知識で十分」と講師の方に
言われても、書店で数冊、書籍を買って、自分なりの納得する点を求めていました。
「そんな事してるから、模試はよくても本試験通らないじゃない」と、言われて
苦虫を噛み潰したような気分でした。
しかし、これが今の実務、業務に役立っているように思います。
今まで司法書士が特にそうですが、「どの司法書士がしても、答えは同じでないといけない」
業務から、「司法書士によって、その業務に対して、どのようなアプローチを出来るか否かの差」
が、出てくる様に思います。
良いも悪いも、誰も経験したことのない「少子高齢化」という社会で
対策、解決策を見出さないといけない時代ですから。
2021.07.30
【追悼】京都産業大学 名誉教授 益川敏英 様
私の母校の京都産業大学の名誉教授でいらした益川敏英先生が他界されました。
心からお悔やみ申し上げます。
ノーベル物理学賞を受賞され、受賞される前から、毎年のようにノーベル賞の受賞者候補として
挙げられ、この受賞者の発表に季節になると、報道陣が大学にやって来るので、少しこの季節は
放っておいてほしい、というお気持ちだったそうです。
私自身は「物理・化学」が苦手で、「慣性の法則」と高校の頃、授業で実験して
どうしても興味がわかなかった事を思い出しました。
理系の方は、頭が硬いと思われがちですが、実は、仮設(発想)に基づいて、
実験をされて、その結果を判断されているので、実は、頭は柔軟でないと、
実験の発想も出てこないと、最近になって思います。
京都大学の山中教授もそうでいらっしゃいますが、
ノーベル賞を受賞される方は、人徳者が多いように思います。
益川敏英名誉教授のご冥福をお祈りいたします。