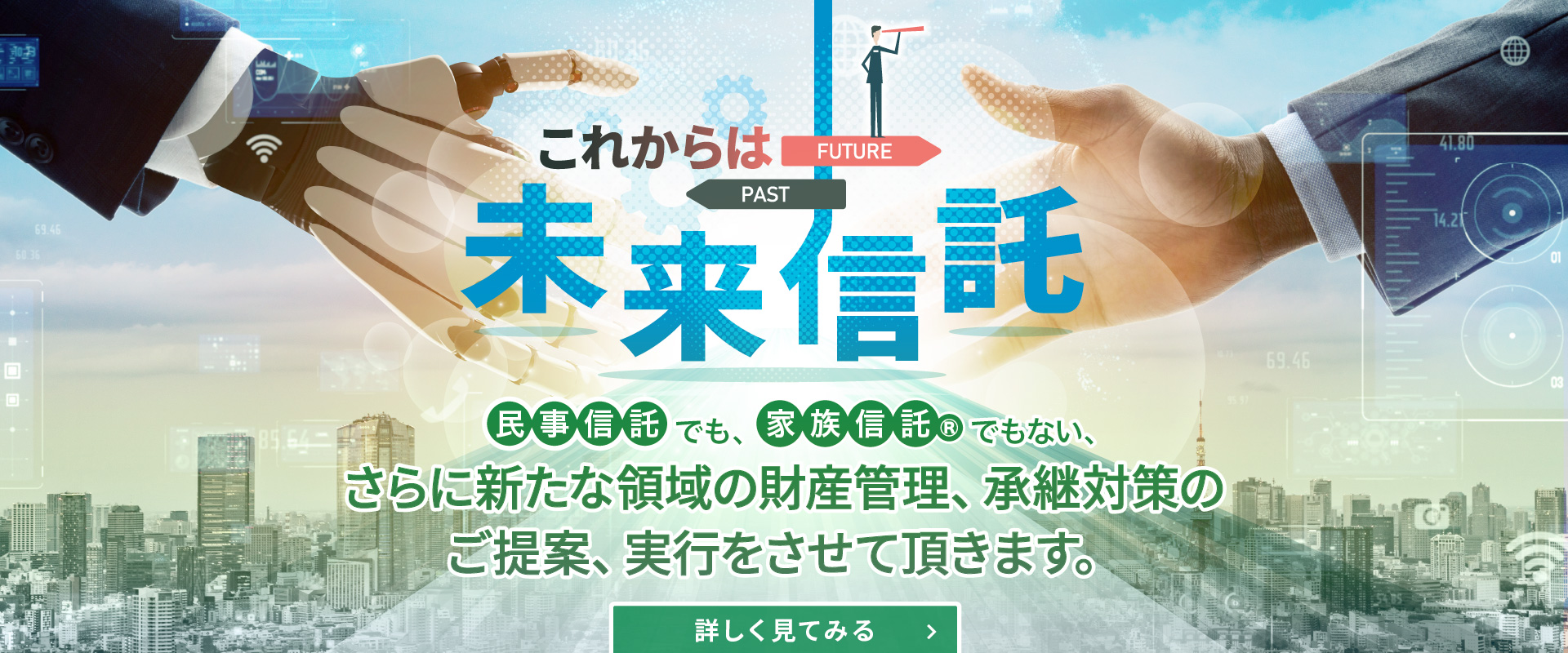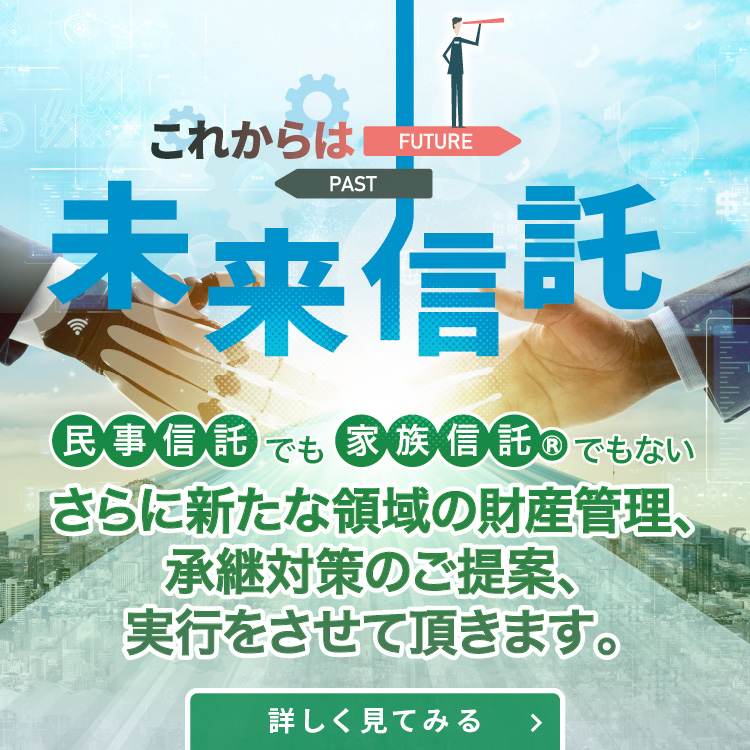ブログ
2020.06.19
分譲マンションを購入された方へ
岡山市内、倉敷市内、さまざまな所で、新築マンションが建設されております。
2000年ぐらいからでしょうか、岡山市のメインストリートの桃太郎大通りが、マンション地域に
なったのは。
2020年の今、築20年ですよね。
分譲マンションは、賃貸マンションと違い、区分所有権を買い、生活するようになります。
よって、大修理、修繕費は区分所有者の方々で負担したければなりません。
販売当時は、販売会社と管理会社が系列会社で安心ですよ、とセールストークをされると思います。
しかし、昨今の社会情勢によって、その企業が将来、存在するか、わかりません。
また、空きの部屋の増加で、マンションの区分所有者が不明、相続登記がされておらず、
誰の意思を確認して、修繕等の意思(議決)をとればよいのか、これから不明になることも
生じると思います。
やはり、きちんとした管理組合を運営される事をお勧めします。
新築当時は、販売会社が運営されているかもしれませんが、管理組合は、居住されている方々で、
ご面倒でもされておくべきです。
購入された当初は、十数年後の修繕等を考えられないかもしれませんが、
すぐに、時は流れ、修繕しないといけない時や、解体の時が来るでしょう。
一人で住居をお持ちなら、相続内、身内内で終わる話が、
マンションになると、数十人の方の3分の2以上の同意が必要になってくることもあります。
くれぐれも、利便性だけを注目されず、管理組合、管理費の運営は、どうなっているか、を
マンションを購入されるときは、ご注意下さい。
2020.06.18
ローソンで「無印良品」が買える!
「ローソン」の一部店舗で、「無印良品」の日用品、雑貨等が買えるようになったそうです。
新型コロナの影響で小売り業が低迷する中、コンビニは前年度より14%の売り上げ増です。
やはり、大きなスーパーや専門店、百貨店が営業自粛する中、身近なコンビニで、色々買えるというのは、
コンビニにとっても、利用者にとっても都合の良い事だと思います。
第2波が懸念される中、業種全体で変革が起こる契機になりそうです。
就職活動にも、変化が起きているようです。
リモート面接による、オンラインを介しての人と人との面接ではなく、
AIが質問をして、それに応えるという面接方法が注目されている様です。
なぜなら、面接官は「見た目の先入観でその人を判断します」が、AIは、
「先入観がなく、客観的に、その人は、どんな能力に長けているのか、短所、長所を客観的に判断できる」
という利点があるからです。
業種によって、求められる才能、能力は違います。AIによって、その人の見えない能力が判断できるので、
コロナが終息しても、採用試験の一部として取り入れる企業が多いそうです。
新型コロナのように、人と接しない様な社会になると、営業マンが必要とされる能力も違ってくると思います。
中国の北京の市場で、再び、「クラスター」が発生したようです。
やはり、中国の食慣習が変わらない限り、新型コロナのような得体の知れない疫病が次から次へと
発生する恐れがありますね。
2003年の「サーズ」の際にWHOから、食慣習の見直しの進言があったのですが、
それが守られていない現状をみると、昔の「マスクをしないでよい」「3密でもよい」といった生活を
取り戻すには、時間がかかりそうですね。
2020.06.17
「遺言書」は、もはや万全の相続(争族)対策には、ならない⁉
昨年の7月1日に改正相続法が施行されました。
この改正において、「遺言書の効力」「遺言執行者の地位」が条文化され、
明確になりました。
「遺言書」につきましては、改正前ですと、遺言執行者を遺言書で指定しておくと、
遺言書の内容に反する相続人の行為は無効になる、とありました。
よって、適法な遺言書が存在すれば、不動産については登記をしなくても、
第三者に対抗(この不動産は私の所有物です)できました。
このような効力が遺言書にあったので、不動産登記をしないままにして、
次の代になったとき、遺言書の存在がわからず、言わば、ほったらかし
の状況で、今日に来ると、俗に言う「所有者不明土地」になっているのかも
しれません。
改正相続法は、「遺言書」の存在だけでは、第三者に対抗できず、
登記等の権利を主張するための対抗要件が必要になりました。
「遺言書」を遺して安心しては、いけません。
きちんと、遺言書の内容を実行してくれる「遺言執行者」を指定しておくべきです。
(ここは、信頼できる方を指定しておいた方がよいです。日頃付き合いがあるところに
任せるのではなく、貴方が他界された後のことを責任もって実行して下さる方を指定される事を
お勧めします。遺言執行者の指定を誤ったため、争う族になる危険性もございます)
「遺言執行者」の地位権限については、改正前は「相続人の代理人」とあり、
さまざまな議論がありました。
本改正によって、「遺言執行者は、遺言書の内容を実行する者」として、明確になりましたので、
「遺言執行者」としての実務多少の違いはあると思います。
近時の判例や裁判例で、「遺言書」の内容が覆される事象がございます。
作成された方は、他界された後の話なので、せっかく相続対策で「遺言書」を適法に遺したのに、
まさに「寝耳に水」といった事象が発生します。
それは、「遺言書」は、あくまで法律上「単独行為」と言って、いない相手にボールを投げる行為
だからです。必ずしも、相手が受けとってくれるかは、わかりません。
また、民法上の法定相続人の権利も発生してきます。
その法定相続にならないために「遺言書」を遺したと思われるでしょう。
しかし、一人の相続人が争う族を発生させ、相続人全員が「遺言書」の内容によらずに、
相続するという事になれば、そちらが優先され、「遺言書」は無きものにされてしまいます。
このような事を知って頂き、相続リスク対策として、民事信託(「親愛信託」)を
ご提案しております。
カテゴリーとして、民事信託は「相続の一部」と紹介されておりますが、
じつは、「民事信託」と「相続」は、まったく別のカテゴリーです。
紹介上、わかりやすく説明するため、に表現しております。
民事信託は、相続によらない「信託法」を根拠規定としており、相続は「民法(相続法)」を根拠としており、
まったく別の専門分野です。実は。
この点を理解されておられない専門家、実務家が実に多い様に思います。
この周辺の法律に関しても、ご相談頂ければ、違いをご説明させて頂き、ご提案させて頂きます。