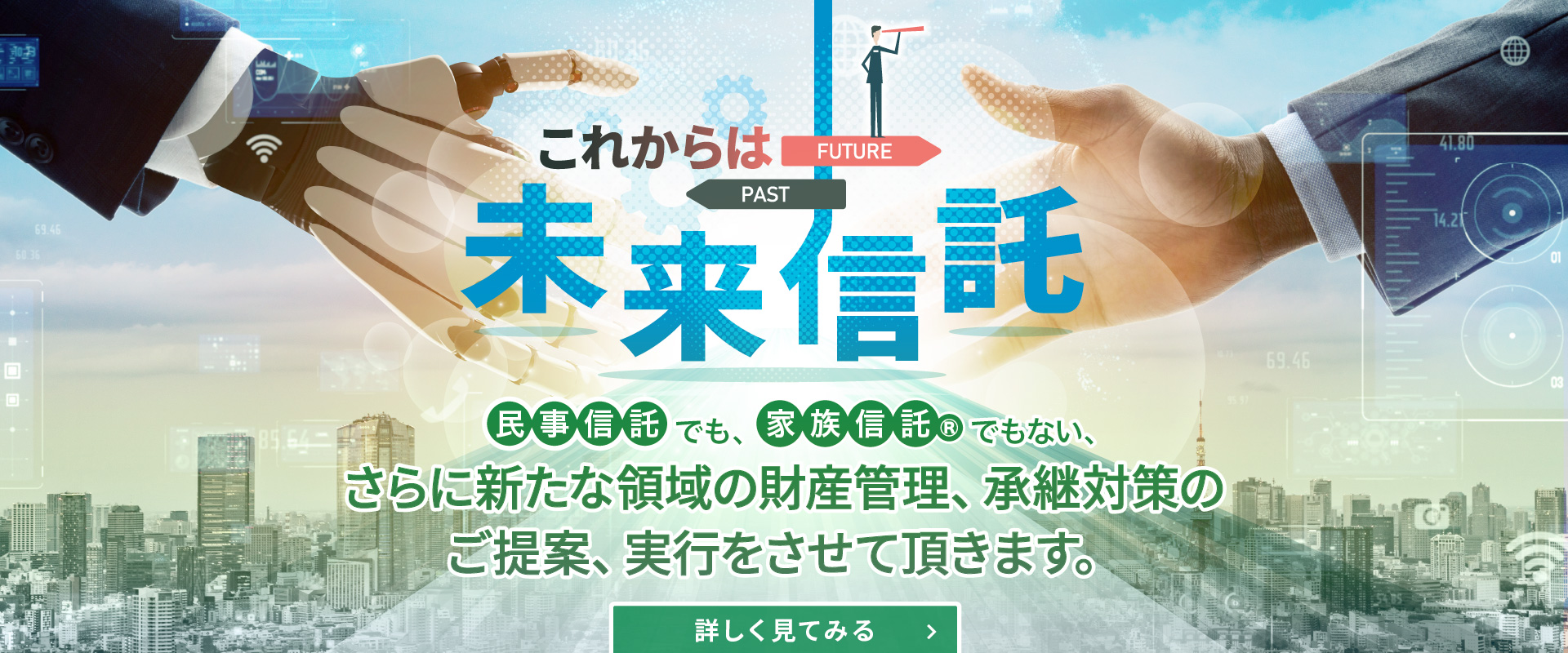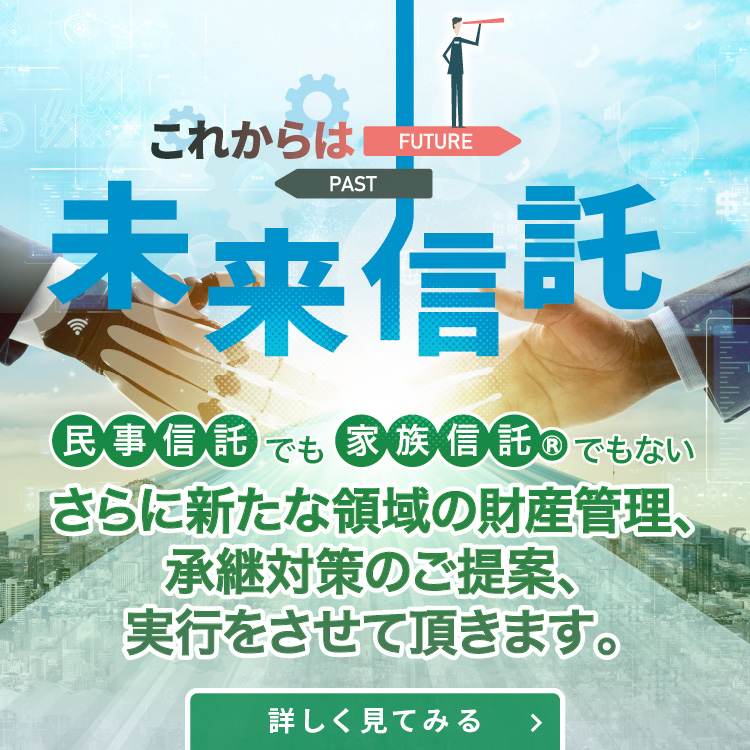ブログ
2020.07.17
「世代交代」
将棋の世界で、皆さん、ご存知のとおり、快挙がなされました。
このニュースを見て、「世代交代」という言葉が死語になりつつあるのかな、と思いました。
僕の好きなプロレスの世界には、「世代交代」というカテゴリーは、よく起こって世代間闘争に
なって、大きくファンを盛り上げてくれました。
最近は、突如、大スターが登場するので、この「世代交代」による闘争は、なくなりつつあります。
日本の一般社会においても、「年功序列」がなくなり、「世代交代」はなくなりつつあるのかも
しれません。
しかし、経営者の世界では「世代交代」が大きなテーマのように思います。
後継者が存在しないので、「世代交代」というテーマにならない企業もあるように思います。
体育会系の育ちなので、「世代交代」と聴くと、昔を思い出して、あの頃の熱い想いが
蘇ることがあります。
やはり、何かと闘うということは、人間の成長において、一定の時期には必要な事だと思います。
「負けてたまるか‼」という、熱い想いが原動力になることもあると思います。
2020.07.16
法務局での「自筆証書遺言」保管制度開始から1週間。
昨年の7月1日から、始まった相続法の改正の一つの目玉である「法務局での自筆証書遺言保管制度」が7月10日より、
開始されました。
原則、遺言書は、自筆で(パソコン不可)すが、財産目録は、不動産では登記事項証明書、預金通帳のコピーで、
足りる事になりました。
なかなか、自筆証書遺言を作成しようとすると、財産目録の作成が難しいというより、ややこしかった様に
思います。
あと、保管先に悩まれていたと思います。今までですと、「遺言信託」という金融機関の商品で手数料が高くつきましたが、
この「法務局での自筆証書遺言の保管制度」は、支払う手数料は、3900円です。
また、自筆証書遺言ですと、遺言書を開封するときに家庭裁判所での「検認手続」が必要でしたが、
この制度をりようされますと、「検認手続」も不要です。
しかし、預かる際の法務局の手続きは、形式的なもので、遺言書として、法的に有効か、という
判断はしてくれません。そこは、あくまで「自筆証書遺言」ということで、ご自身で書いて下さい、とのことでしょう。
よって、是非、この制度をご利用される際は、我々、専門家にまずは、ご相談下さい。
折角、遺されようとした、貴方のご遺志が、後世に伝わるように、法的に有効になるように
アドバイス等させて頂きます。
その際は、色々なお話も伺いながら、アドバイスさせて頂きます。
2020.07.14
『流れ星をみた瞬間に願い事を言えれば叶う』のは、なぜでしょうか?
子供のころに、『流れ星を見た瞬間に願い事を言えたら、その願いが叶う』と聴いたことは、
ありませんか?
大人になり、子どもに『どうして、流れ星に願い事をすると叶うの?』と、
質問されて、皆さん、答えられますか?
この話題は、実はラジオの夏休みの子供に向けての企画で、『子ども何でも相談室』で、
あるラジオのパーソナリティーが、大人も納得のいく答えをしました。
それは・・・
『流れ星は、一瞬だから、その瞬間に願い事が浮かぶのは、その願い事のために
毎日、叶えるために頑張っているからだよ。一瞬で浮かぶのは、いつも、その願い事を
頭の中で実現できるように、生活しているからだよ。』
なるほど!
すぐに思い浮かぶのは、いつも、その願い事を考えているから。
皆さんは願い事はありますか?
あのお笑い怪獣が、神様にお願い事をするとしたら、の回答に
『悩み事がなくなりますように』と、答えました。
さすが。言葉を操る天才ですね。