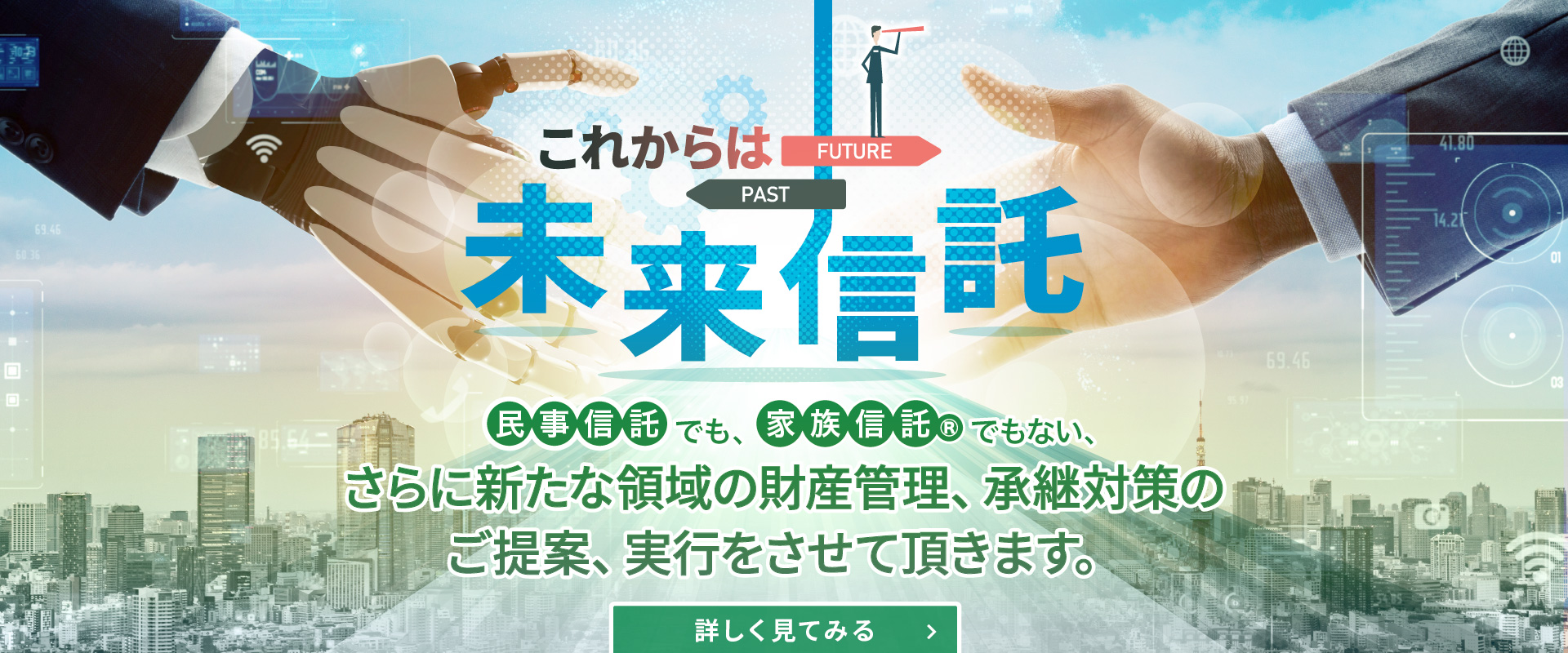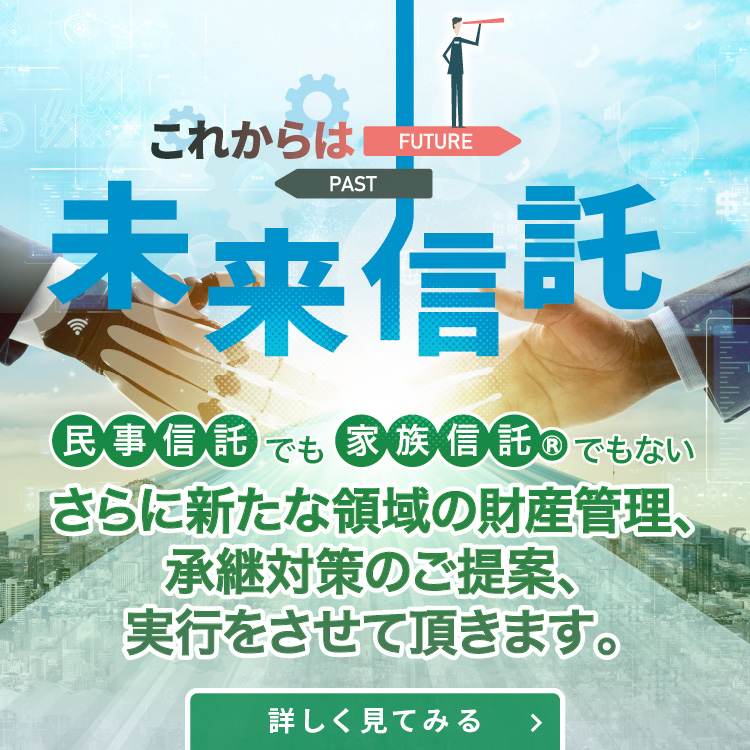ブログ
2020.11.17
特殊詐欺サイトの見分け方
近年、巧妙さを増している特殊詐欺。
詐欺をしている者は、罪の意識を低下させるため、普通のサラリーマンの
様に、会社に出社して、営業成績で報酬が決まる、という徹底したものです。
NHKの特殊詐欺の再現ドラマを観ましたが、「営業をしているように詐欺をさせる」
もちろん、犯罪行為をしているのですが、それが、あたかも被害者を増やすことは、
営業を獲得したかのように思わせるもの。
人間が慣習化したら、始めは罪の意識もあるのでしょうが、それはごく当たり前の仕事に
なってしまうのが人間の怖いところです。
営業部長や、課長、係長と役職もあり、詐欺事件の件数ならぬ営業成績となり、昇進も
詐欺組織にはあるようです。
メールやサイトの「まがいものホームページ」の見分け方があります。
それは、漢字の表記がおかしい、日本語の表記が変、アドレスが微妙におかしい点が
挙げられます。
ほんの些細な点で、見分けることができます。
そこまで巧妙に大手企業のホームページに似せている点も注意すべきですね。
逆に言えば、日本の大手企業の信頼性が高いこともいえると思います。
詐欺集団は、有名企業に似た企業名や、日本の官公庁の出先機関を名乗って詐欺をする場合が
多いです。そこも、日本人が信頼している点に付け込んでいるのでしょう。
何か請求されたら、誰かに相談する事が一番です。
詐欺集団は焦らせて、詐欺を働くのですから。
2020.11.11
「人質」ではなく、「情報質」。
「おまえの子どもを誘拐した。無事返して欲しければ、身代金1億円用意しろ!」
と、刑事ドラマでの誘拐事件でのよくあるシーンですが、
今のターゲットは、「人」ではなく、「会社の情報」のようです。
ある日本の有名なゲームソフトの企業が、サイバー攻撃を受けて、
会社のシステムに侵入され、情報を暗号化され、「情報」を盾に
お金を要求されているようです。
「指定した金額を支払わなければ、情報を流す」という脅迫のようです。
情報も会社のシステムも支配され、それで金銭を要求するとは、時代ですね。
それほど、我々のパソコンも狙われている認識を持たないといけない時代ですね。
確かに、パソコンがなければ、このコロナ禍、オンライン会議も出来ないですし、
データもパソコン内なので、支障が大きいですね。
くれぐれも、気を付けたいものです。
2020.11.10
プロレス業界も2強の時代へ
アメリカの大統領選、トランプ現大統領は今後どうするのでしょうか?
アメリカは2大政党制により、政権交代がよりしやすい環境にあります。
今回も共和党から民主党への政権交代ですね。
ところで、日本のプロレス団体、いくつあるか、ご存知ですか?
大小合わせると、10以上もの団体が存在します。
といっても、圧倒的な1強です。
「新日本プロレス」の1強時代です。
このコロナ禍でも、来年の1月4日の定例に東京ドーム開催に加え、
5日も東京ドームで大会を開催するそうです。
一方、三沢光晴さんが設立された「NOAH」と「DDT」というプロレス団体が
サイバーエイジェントの経営の元、統合し、大会を開催するようです。
ある意味、業界の再編ですね。
団体の垣根を超えて、それぞれ団体ではなく、ユニット単位でプロレス界を
盛り上げてくれそうです。
やはり、業界は2強の時代になるようですね。