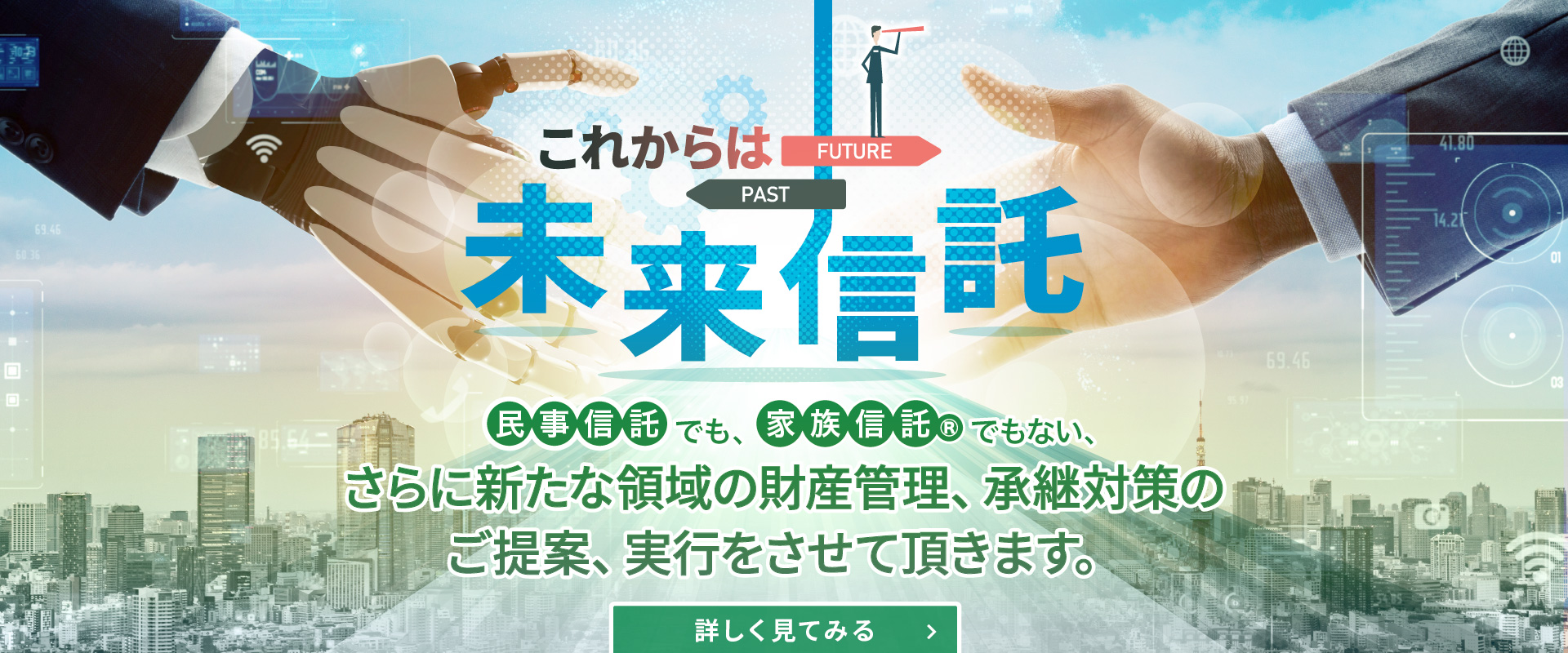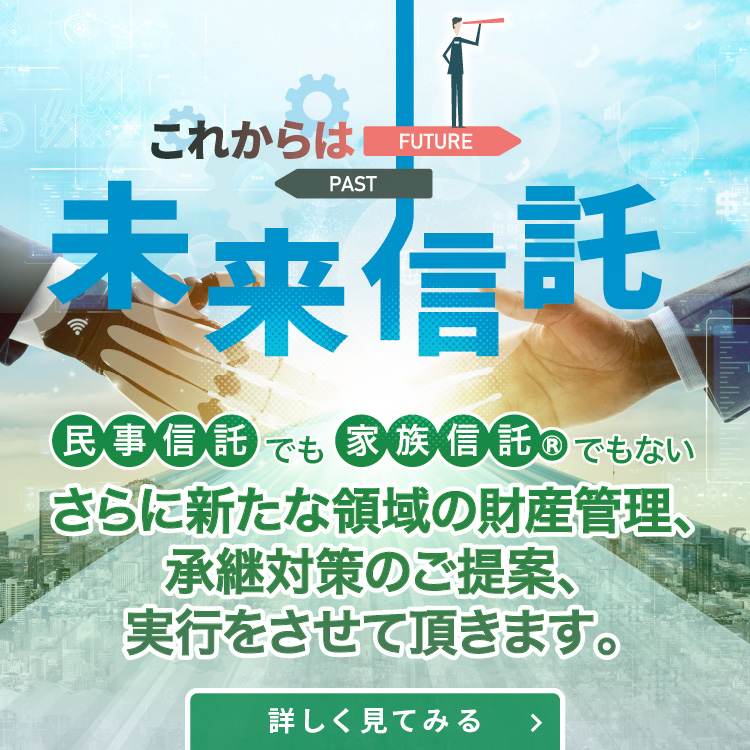ブログ
2021.04.28
「ペット信託®」の重要性
今朝、和歌山のドン・ファン こと資産家の方の殺人事件について、
元妻の方が容疑者として逮捕されました。
この事件が世間をにぎわせた時、その資産家の方が愛犬家という事で、
「ペット」のための「民事信託」すなわち「ペット信託®」が話題になりました。
ワイドショーのコメンテーターの方がおっしゃっている内容は、まったくの間違いだった
事を覚えています。
どうしても日本人には「信託」は財産を殖やす金融商品のイメージが強くて、
ようやく「家族信託®」=「認知症リスク対策」ということで、イメージが浸透して
いるように思います。
しかし、信託法を根拠とする「民事信託(親愛信託)」は、財産管理、資産承継の
方法を民法ではない、やり方を示したもので、歴史によって作られた法律ですので、
とても奥が深く、積極財産なら信託財産にする事ができます。
また、「委託者」「受託者」「受益者」も、特別な規定は少なく、
当事者になることも多いに可能性があります。
ペットの飼育については、民法では「負担付遺贈」等で検討されていましたが、
この方法では、ペットは主役の契約ではなく、お金を渡す代わりにペットを
育てて下さい、というお金の譲渡がメインで、ペットの飼育は言葉のごとく「負担」
なのです。
これでは、大切にしていたペットの将来に不安が残ります。
しかし、「ペット信託」はペットと不動産、金銭等、同じ信託財産であり、
同じ運命をたどります。
それも、託す相手は、信頼できる方に契約という形で基本的には行います。
また、「ペット信託」をご提案、実行させて頂いた、我々、専門家も見守ります。
そこで、今までにはない、ペットに明るい未来をご提供できます。
是非、この「ペット信託®」を活用して、ペットとの楽しい生活をして頂きたいと
思います。
2021.04.26
「FIRE」という生き方
「FIRE」…「F FINANCIAL」「I INDEPENDENCE」「R RETIAR」「E EARLY」
訳すと、経済的に将来、生活できるだけの資産をもって、早く退職する。
という「生き方」が20代、30代で注目されているようです。
そのために、給料の8割を資産運用に回して、生活費は節約する。
年収の25倍に資産ができたら、定職を辞めて、自由に生活をする。
そんな「生き方」を「FIRE」と言うらしいですね。
「自由」とは、響きがよいのですが、そこには必ず、「責任」が問われます。
「そんな事、知っているわ、オッサン」と、反論されそうですが。
どの業種、どのトレンドも第一人者や先駆者が生計を立てられるので、
「憧れ」としては、いいかもしれませんが、目的になってしますと、
人生、ほんとうに「FIRE」で楽しいのだろうか、と疑問に思います。
その世代、その世代に応じたお金の使い方、付き合い方を学んで、
そこに、自分の人生があると思うのですが。
「憲法第13条 幸福追求権」があるので、それは、それと、
職業柄、許容はできるのですが、もし、自分に置き換えると、
「FIRE」という選択肢は、ないかな、と思います。
2021.04.23
本屋さんで『自分で一人で出来る~』という本を見ての雑感
『終活』や『相続・遺言書』『自分でできる相続登記』等々、よく本屋さんで見かけて
少し中身を見たりします。
時には、ご相談者の方が『○○』という本を見たのですが…
と言うご相談のために、その本を実際に買って読んでみたりします。
皆さん、ご存知だと思いますが、注意、留意して頂きたいのは、
本、書籍になっているからといって、内容が本当に正しいとは限りません。
本、書籍を出すのは、憲法上、『表現の自由』というものの範疇で、
「本の通りしたけど、上手く進まないじゃないか」と、専門家の著者を
訴えても、「表現の自由の範疇で、信じた貴方が悪い」という結果に
実際にはなります。
弁護士が法に触れないといって行った行為が、実際には法に反する場合は、
弁護士が直接、罰せられるのではなく、その行為をした方が罰せられます。
よって、情報過多の現在、きちんとした法律家や税理士などに費用がかかっても、
直接、ご相談されることをお勧めします。
人間同士なので、『合う、合わない』とがあると思いますので、
是非、気の合う専門家とお付き合い下さい。
「最近、本を読んで、法務局の無料相談に行って、なんとか自分で相続登記を
しようとして、でも時間がかかって、仕方ないので、お願いにきました。」
という、ご依頼者さんが多いです。
その収集した書類を拝見すると、必要ない戸籍や重複している書類など、
時間と費用がかかったんだなと、実感する事が多いです。
まさに「餅は餅屋」です。
最低限の知識で、勉強されるのは良いと思いますが、
実務をすると、色々ございますので、是非、専門家のご利用をお勧めします。