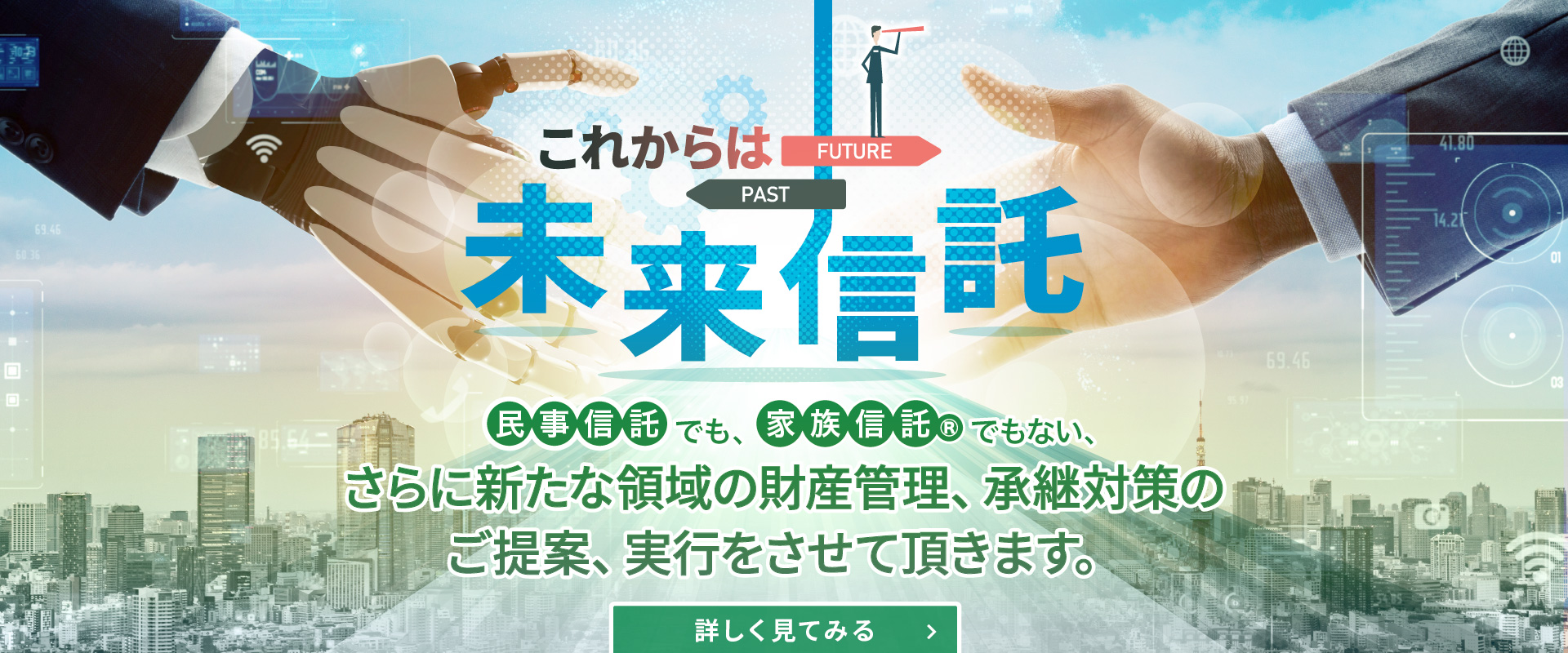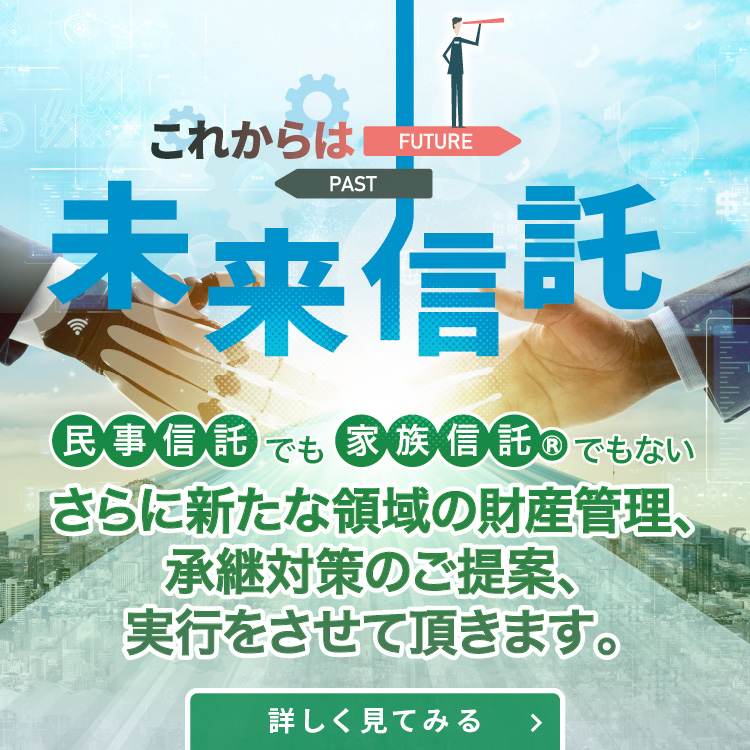ブログ
2022.02.01
相続土地国庫帰属法の新設
民法、相続法、不動産登記法の改正と伴に「相続土地国庫帰属法」が新設されます。
でも、国が引き取ってくれる土地については、私見ですが、ハードルが高い様に思います。
①更地でないといけない。
②担保権等の設定がない。
③境界紛争がない。
④土壌汚染がない。等々
日本国憲法に私有財産制度があるので、民間の土地については、
私的自治で、国が関与しない原則の中、ある意味画期的な対策に思えますが、
どれだけの方が利用されるのでしょうか?
該当する土地に関しての審査もあり、中々、実務運用が難しそうな気が致します。
細かいところの法律の改正もございますので、また、情報提供させて頂きます。
2022.01.31
昨日、セミナーにご参加頂いた皆さまへ
昨日は、有限会社西孝主催の「相続・資産承継セミナー」にご参加頂いた皆さま、
ありがとうございました。
来月は、「資産承継」の肝である「民事信託」と「民法・後見制度」と「民法・相続」に
ついて、お話させて頂きます。
平成18年に施行された信託法。
今までの日本の法律の概念にない事が条文化され、なかなか、運用できる実務家が存在しません。
事務所開業当初から、民事信託に関心を持ち、信託法も条文についても、研究し
アメリカ、イギリスでの運用から、日本の信託法をどう活用すべきか、
師匠で民事信託の第一人者で、実務家としても多くの経験をお持ちの河合保弘先生と
実務に当たりながら、最近の裁判例を研究し、皆さまのお役に立てるように、
日々、研鑽しております。
私も実務経験がございますので、どのようなケースが具体的にお話させて頂きます。
次回、2月27日(日)13時30分から岡山県健康づくり財団の会議室にて開催致します。
2回目からのご参加でも、ご理解頂ける内容になっております。
有限会社西孝 岡山市南区西市858番地リバティー1階
086-805-0350 まで お問い合わせください。
2022.01.28
相続対策ではなく、資産承継対策へ
相続=法定相続人、法定相続分、遺産分割協議、遺留分侵害額請求
☞ 唯一の解決策とされていた。
遺言書=「争族対策は遺言書で万全」
家族信託®=「認知症リスク対策」
このような考え方の学者、法律専門家あるいは、税務関係の専門家まで
これが「正しい」と思い込んでいる方々がいらっしゃいます。
上記の実務内容では、専門家という職業は必要とされなくなるでしょう。
私も民事信託を活用した予防法務とリスクマネジメントを中心に業務をさせて頂いております。
ご相談を受ける中で、民法では解決できない社会が実際に存在します。
しかし、予め、各種の専門家の知識、知恵を駆使すれば、解決できる事もございます。
そうです。
医療と同じく、予防策は重要ですし、選択肢は沢山ございます。
しかし、事後処置になると、選択肢は限られます。
昨日、ブログでお話させて頂きました様に、各家族、各企業にかかりつけ法律専門家がいれば、
重症にならずに、終わる、問題にならないうちに終わる事象もございます。
私も民事信託を生業にしておりますが、信託は認知症リスク対策がメインでは、ございません。
硬直化していると批判し、家族信託®の有用性を説く家族信託®専門家が多いですが、
実は、成年後見制度も見直し、銀行業界も現行の後見制度と違った運用を始めると、
新聞にリリースされていました。
(随時、情報提供をして参ります)
10年昔ではなく、3年昔と言った様に時代の流れ、制度の変更はこれから目まぐるしく
起こることは、容易に想定できます。
士業が資格取得の試験勉強の知識で、業務が出来る時代は終わりました。
情報を収集して、考察して、皆さまにお役に立てるご提案、解決策、予防策を
これからも模索して参ります。