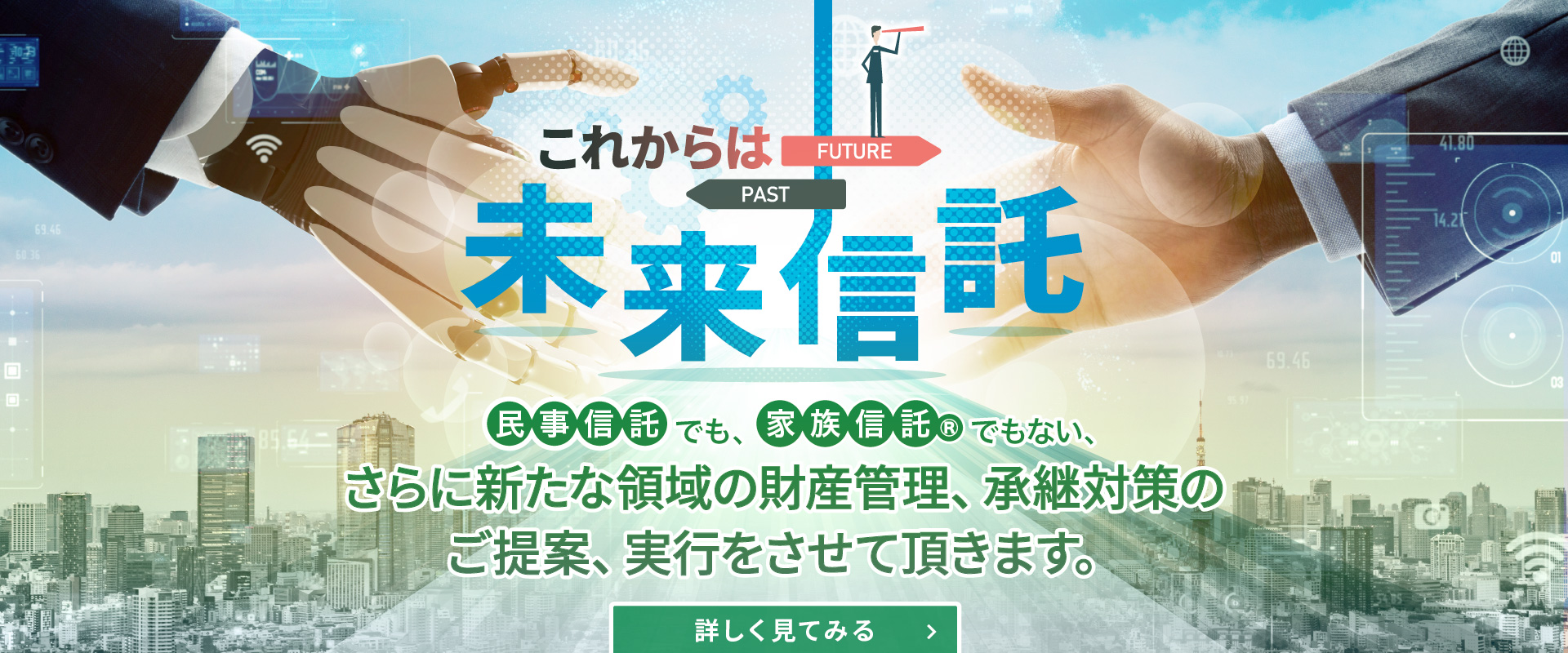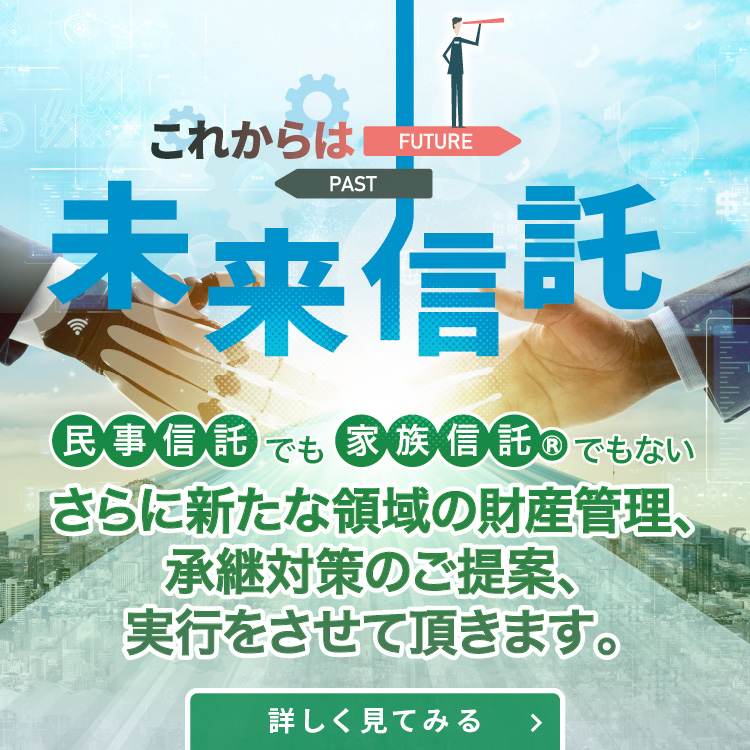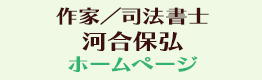お知らせ
2025.09.11
【法律考察シリーズ第1弾】民法第90条と日本国憲法との繋がり。
今回から、私が大学生時代に研究した事、司法書士受験生時代に勉強した事、司法書士となり実務からみた法律の観点から
実は、法律には、あらゆる側面があり、様々な社会、各法律との繋がりをご紹介したいと思います。
第1弾としまして、「民法第90条」です。
必ず、各国家資格試験を受験される方には必須の法律条文です。
多くは、「愛人契約」、「殺人契約」とかで、「契約は公の秩序に反するものは取消できる」
と言う事で、専門家が話しておりますが、実は、これ以外にも大きな役割がこの条文にはあります。
それは、日本国憲法との繋がりを持つのが、民法第90条です。
憲法は、国家対国民の間を規定する法律が原点ですが、
歴史上、修正され、国家からの自由、国家への自由(参政権)、国家による自由(社会立法と呼ばれる、
労働法、消費者保護法など)で、国家も国民の自由を保障するためには、一定の役割、私人間への介入を
要求され、原点とされる憲法の概念から修正されました。
私人間で紛争が起きても、民法によって解決すべきとされるのが憲法の立場ですが、
人権の尊重からすると、現実社会において、会社(雇用主)と使用人(会社員)とでは、
対等に契約をすること事態、困難な場合があります。
やはり、会社の方が強く、会社員の方が立場上弱い事が殆どです。
そこで、この民法第90条では、公の秩序として、無理難題を押し付ける会社との
契約は取り消せる、と多くの判決がございます。
あまり知られておりませんが、ホストがお客さんの料金の「ツケ」をホストにお店が
持たせることは、この民法第90条により無効(かつては、無効でした)とした判例が多くございます。
私人間同士でも、立場上において対等ではない場合は、この民法第90条が適用される事は、
日本国憲法の「法の上での平等」を実現させるために、その役割を担っております。
法律も一見すると、難しい事ばかりではなく、実社会の中に存在するものなのです。
こうしたトピックを今後、ご紹介していきたいと思います。
雑学の参考にしてください。